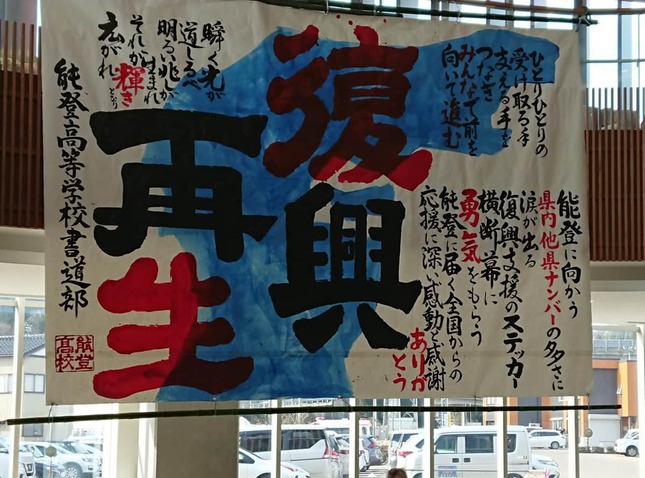津波のニュースを聞き、即座に現地での支援を決めた。向かう先は、能登半島。片道約700キロ、車で10時間ほどかかる。それでも――。
宮城県東松島市は、2011年3月11日の東日本大震災で、津波による甚大な被害を受けた。それから13年。同地で運営されている防災体験型の宿泊施設「KIBOTCHA(キボッチャ)」スタッフと東松島市民が、能登半島地震の発災直後から支援に動き出した。
現地入り決めた理由は「津波」
能登で大地震が起きた2日後の24年1月3日、「KIBOTCHA」の運営会社「貴凛庁」の三井紀代子代表は石川県に入った。能登町の行政とつながりがあり、避難所での炊き出しを申し出たところ、快諾される。KIBOTCHAからは、支援第2陣、第3陣が、地元・東松島で集めた物資をワンボックスカーいっぱいに詰め込み、能登へ向かった。
1月4日、能登町で炊き出し開始。地震で道路があちこちで寸断され、十分な物資が届いていなかった時期だ。豚汁と、おにぎり。「温かい食事を、皆さん喜んでくれました」。ここから連日、食の面で町民を支えていく。
KIBOTCHAとして、発災直後に被災地で直接支援にあたるのは初めてだ。「超」が付くほど遠くから、迅速に現地入りを決めた理由は「津波」だったと、三井さんは明かす。
東松島市は、東日本大震災で死者・行方不明者1133人(市発表、21年3月11日時点、死者数は災害関連死66人を含む)をはじめ、多大な被害が出た。KIBOTCHAのある野蒜(のびる)地区は、浸水高が最大で10.35メートルの津波が押し寄せた。能登半島地震でも、元日の発災時から津波のニュースが流れた。長期の停電や断水、厳しい冬の寒さと、被害の大きさは容易に想像できる。
「東日本大震災を経験したここ東松島から、支援に向かおうと決めたのです」
被災を乗り越えた人が支援「ホッとした顔をしてくれます」
炊き出しの食材や支援物資の供給を支えるのは、KIBOTCHAのスタッフ、そして東松島のボランティアだ。「汁もの」に使う野菜は、東松島市の農家から続々と寄贈された。それらを、KIBOTCHAのレストラン部門で働く人たちが中心となってカットする。鮮度を落とさない装置を使って、能登へ運ぶ。この繰り返しだ。
震災を経験した土地の人ならではの知恵も。最初に能登へ向かう車には水や毛布、カイロの他、「災害用トイレ」3つが詰め込まれた。自治会長がその必要性を見越して、持たせてくれたという。実際に能登町では、トイレに困っていた避難所で大いに重宝された。
1月22日からは、再開した学校での「給食支援」になった。授業は月曜日から金曜日まで。金曜夜から週末にかけて、能登町から東松島市へ戻り、カット野菜や必要物資を調達して、また能登へ戻る。三井さん自身「何往復したか、覚えていません」と明かす。
ある日、輪島市の教育長から三井さんに連絡が入った。学校給食の提供見通しが立たない同市の学校で、給食支援をしてほしいとの要請だった。能登町に拠点を置いたまま、2月中旬からは輪島市でも活動をスタートした。市内では小中高の生徒が集まり、3か所に分かれて学校生活を再開させている。給食時間になると、副菜として「汁もの」を配った。豚汁、トマトスープ、コンソメスープ、卵とじスープ。
「子どもたちの一番人気は、カレーです。おかわりに来る子もいるんですよ」
温かい食事は、身も心も元気にしてくれる。東松島市の人たちも13年前、被災後に支援者が来て炊き出しをしてくれたのを、今も覚えている。KIBOTCHAで野菜を刻みながら、車に支援物資を詰め込みながら、「恩返し」という言葉を誰もが口にしていたと、三井さん。
「能登へ出発する前、地元の人から『私たちも大変だったけど、今は元気で頑張ってるから、皆さんも大丈夫よって伝えてね』とメッセージをもらいました。能登の皆さんは、被災経験を乗り越えた宮城から来たと知り、ホッとした顔をしてくれます」
今は苦しい日々を送る被災者も、その先に光がある。東日本大震災を経験しながらも、今は前を向いて暮らしている支援スタッフの言葉には、説得力がある。
3月に入っても、輪島市ではまだ大勢の人が避難所での暮らしを余儀なくされている。厳しい状況は続く。それでも、被災の痛みを知る人たちがきょうも、おいしくて暖かい食事の準備を続けている。(J-CASTニュース 荻 仁)