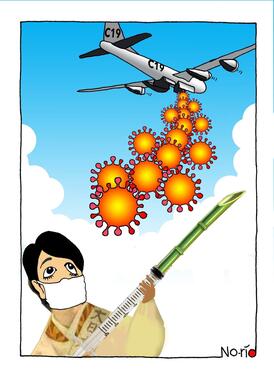コロナ禍は、あらゆる学問の分野に挑戦状を突きつけた。これまで蓄積した知見を総動員して、いま、何が言えるのか。あるいは、これまでのアプローチに欠けていたものは何だったのか。コロナ禍は、歴史学の分野でも、再考を迫っている。
昨年12月、『コロナの時代の歴史学』(績文堂出版)という本が刊行された。歴史学研究会が編集し、16人の歴史家がコロナ禍に向き合って思索を重ねた論文集だ。まだ感染の行方が定まらない時期に企画し、執筆依頼から締め切りまで2か月もない慌ただしさのうちに出版された。長い時間軸を前提に過去を振り返る歴史家たちが、感染が同時進行中のこの時期に、なぜ緊急出版を目指したのか。監修にあたった中澤達哉・早稲田大教授と、三枝暁子・東大准教授のお二人に2021年7月21日、Zoomでお話をうかがった。
歴史家の「当事者性」
歴史学研究会は、1931年2月、東京帝大文学部史学科の若手ら数人が結成した「庚午会」の流れを汲み、翌32年12月に結成された民間学術団体だ。それまでの権威主義的な歴史学に対して進歩的、近代的な立場をとって33年には機関誌「歴史学研究」を刊行。急速に「皇国史観」に染められる学界に対して抵抗した。
1931年9月には満州事変が起こり、国内の言論は急旋回しようとしていた。1935年には、それまで通説だった美濃部達吉の「天皇機関説」に対する排撃が始まり、「国体明徴運動」が盛んになった。東大も国史科の平泉澄らが中心となり、日本思想史講座で「皇国史観」を説くようになる。こうした動きに対し、南原繁は、1939年に法学部内に東洋政治思想史の講座を設け、津田左右吉を講師に招いて抵抗するが、津田の本も発禁処分になり、講座を託そうとした弟子の丸山真男も二度にわたって召集される。歴史学研究会も、44年には活動停止を余儀なくされ、戦後の1946年にようやく活動を再開して今に至る。
2020年5月、歴史学研究会は毎年恒例になっている大会を、コロナ禍で延期せざるを得なかった。これは1944、45年の戦争末期を除けば、90年近い歴研の歴史においても初の出来事だった。
その5月に、新旧四役会議がオンライン方式で開かれ、この本の企画が持ちあがった。コロナ禍であらゆる活動は停滞しつつあったが、「感染症の流行に、ただ影響されているばかりでよいのか。このような状況だからこそ発揮すべき歴研、歴史学の力があるのではないか」という意見が出された。
新年度委員会は、若尾政希委員長、北村暁夫編集長が留任し、本の企画は旧年度事務局長の中澤達哉さん、研究部長の三枝暁子さんに託されることになり、事務局員の増田純江さんの協力も得ながら刊行作業を進めることとなった。それが、この本ができるまでのいきさつである。
もともと2020年度の大会で予定していた全体会のテーマは、「『生きづらさ』の歴史を問う」だった。結局、大会は延期され12月に開かれたが、今回の企画の前提としてあったのは、歴史家が「当事者性」をもって歴史をとらえることの重要性だったという。研究部長だった三枝さんはこう話す。
「非正規雇用の急増や、うつの増加、学生や院生が貸付型の奨学金に頼らなければ学業を続けられないなど、私たちの周りにも、『生きづらさ』は身近に迫っている。歴史学も新自由主義のひずみを問題にし、その起源を探る試みを続けてきましたが、より強い当事者性をもって『生きづらさ』に向き合うべきではないか。そんな問題意識を抱いて大会を準備していたところに、「コロナ禍」が広がった。後から歴史として振り返られる事件に私たちは立ち合っている。歴史家にも、現在をどうとらえるか、という問題が突き付けられている。そうした一種の使命感が芽生えたところに、『こんな時こそ、何かできないか』という執行部の思いが重なり、企画が動き出した。短い時間に完成できたのは、異様な緊張に包まれていたからだと思う」
続けて中澤さんはこう語る。
「今世紀になって、リーマン・ショックや東日本大震災など、後で振り返ると歴史に残る出来事が多く起きた。しかし今度のパンデミックは死者数からいっても、大戦に匹敵する大きな衝撃だった。歴史学は予言の学ではないし、未来を予測することを目的に過去を調べているのでもない。でも、歴史学ほど現状認識とかかわる学問もない。だから、今後の歴史学はどうあるべきか、という点については、同時進行の今においてこそ議論すべきではないか、と思った」
「グローバル・ノース」の歴史学
集まった16編の論文は、次の七つの章に分かれている。
第1章 感染症拡大の歴史的再検討・歴史学の位置
第2章 医療史・公衆衛生史のなかの感染症
第3章 感染症をめぐる政治と社会の分断・緊張
第4章 感染症による現代国民国家の変質
第5章 感染症が照らしだす人種と差別
第6章 感染症をめぐる格差・労働・ジェンダー
第7章 感染症と歴史実践
この章立てを見てもわかるように、この本は、これまでの歴史学の蓄積を踏まえ、コロナ禍が浮き彫りにした問題群をどう位置づけるかという問題意識に貫かれている。中澤さんはこう話す。
「今回特徴的だったのは、感染症が広がる過程で、これまで隠蔽されてきたものが可視化された、ということでした。米国におけるブラック・ライブズ・マター運動から、ハンガリーなど欧州における権威主義体制への移行に至るまで、それまで見えていなかった潮流がコロナ禍で顕在化した。あるいは世界におけるジェンダーの問題やレイシズムが鮮明になった。そうした論文の中で、私がとりわけ強い印象を受けたのは、我々の研究が『グローバル・ノース』の歴史観に制約されていたのではないか、という指摘でした」
たとえば千葉大の小沢弘明さんは、「新自由主義下のCOVID―19」という論文の冒頭に、WHOが2016年に調査した所得別の死亡原因トップ10の図表を掲げる。これを縦軸に順位、横軸に「全世界」と「高所得国」から「低所得国」まで4つのカテゴリー別に死因を並べたものだ。高所得国では「虚血性心疾患」「脳卒中」「アルツハイマー病」が上位3位を占め、「下気道感染症」は8位。これに対し、「低所得国」では「下気道感染症」が1位、「下痢性疾患」が2位、「HIV/AIDS」が4位、「マラリア」が6位、「結核」が7位と、感染症が五つまでを占めている。
小沢さんは、こうした違いから、感染症に囲まれた「グローバル・サウス」がその死を社会的・構造的にとらえているのに対し、豊かな「グローバル・ノース」は感染症を一時は抑え込んだと思い込み、パンデミックをいまだに「事件史」としか把握していない、と指摘する。つまり、私たちはグローバル・サウスの感染症を他人事としてしか考えてこなかった。歴史学も、そのもとで制約されてきた、というのだ。
小沢さんはさらに、私たちはすでに40~50年にわたって「新自由主義」を前提に生きており、医療や介護システムを競争的・効率的なものに変えるため、市場化の対象にしてきた、という。今回のコロナ禍にあたっても、政府はデジタル化やリモート化など医療産業イノベーションを急激に促進する「好機」ととらえ、危機を利用した資本主義の再編強化を狙っている。つまり「ニューノーマル(新常態〉」は「第4次産業革命」という資本主義の新たな形態に照応した言説体系を構成している、という。
小沢さんはこうして、歴史学もまた、グローバル・ノース、新自由主義の制約に置かれ、パンデミックの克服も「パンデミック資本主義」のもとで進むという逆説を示す。そうした逆説を見据えることを、「事件史」から脱却する出発点にすべきだ、という覚悟を示したといっていいだろう。この論文について、中澤さんはこういう。
「北半球の歴史家は、初めてパンデミックに直面して、慌てるしかなかった。これまで歴史家はグローバルヒストリーの重要性を説いてきてはいたが、実際にはグローバルな世界史を真剣に考えてこなかった、ということだろう。これも、コロナ禍が初めて突きつけた課題だったことを指摘した論文だった」
私たちの歴史観が普遍的なものではなく、むしろ地理的、時代的に制約されたものであることを、別の角度で論じたのは、東大の池田嘉郎さんによる「コロナ禍と現代国民国家、日本、それに西洋史研究」だ。
池田さんは、今回のコロナ対応において、欧米の対応は日本にとって、「包括的モデル」として機能しなかったことを指摘する。欧米を見習うべきモデルとする傾向は、近代批判が登場した1970年代からすでに色あせていたが、今回のコロナ禍で「包括的モデル」としての欧米は最終的に失墜したという。
歴史家にとって、その意味は大きい。明治時代に日本の歴史学は三つに区分された。「西洋史」「東洋史」「日本史」である。池田さんが研究の足場とする「西洋史」は、もともと、「包括的モデル」としての西欧という世界観を出発点にしていた。それが「失墜」したというのなら、当然「西洋史」研究の在り方も問われる、と池田さんはいう。
そのうえで池田さんは今回のコロナ対応において、私権の制限をできるだけ避けるという日本の「ソフトな対応」は、決定や実行の遅れという批判にさらされながらも、「包括的モデルとしての西欧に由来する議会制、市民社会、私権といったものを尊重した点にこそ特色があった」と指摘する。その意味で、「西洋史」という枠組みはなお意義を失っていない。
だがそれ以上に重要なことは、コロナ禍をきっかけに、日本社会は外部に包括的なモデルをもつことなく、21世紀を進んでいかねばならない、とも指摘する。「おそらく、どこかに包括的なモデルをもつという発想自体が、日本だけでなく世界的にみて、過去のものとなったのかもしれない」と池田さんはいう。
「中世」からのまなざし
歴史学の立脚点を問われたのは西洋史に限らない。三枝さんは14世紀から17世紀にかけての日本史をフィールドにしてきたが、コロナ禍をテーマにすることが決まって、自分の研究が今の時代にどう結びつくのか、無頓着でいたことに気づいたと振り返る。
「歴史学では、史料をもとに実証可能なことを着実に究明する姿勢を求められます。そこから飛躍して何かを論じることには慎重な人が多い。今回初めて、今起きていることに対し歴史家として何が言えるのかを、問われたような気がします」
三枝さんは論集に「感染症と中世身分制」という論文を寄せた。この論文で三枝さんは、今回のコロナ禍で感染者やその家族、医療や流通・小売りなどリスクを取って働かざるを得ない人々への差別が生じたことに焦点を合わせ、感染症が差別の原因となり、社会構造の矛盾をあぶり出す状況を過去にさかのぼって考察する。その例として、中世日本におけるハンセン病の罹患者が共同体から排除され、身分制の最下層をなす「非人」集団に組み込まれたことを、さまざまな史料をもとに論じている。
こうしたことが起きた背景には、中世の京都を中心に広まった「穢(けがれ)」観念と「宿業(すくごう)」観の流布があったという。王朝国家は感染症に代表される「ケガレ」をどう解消するかに心を砕いた。
だが、権力が排除の観念やイデオロギーを流布したとしても、それを厳格に遂行する主体がなければ、差別や排除は社会に行き渡らない。
三枝さんは非人宿を束ねる長吏による起請文などをふまえ、ハンセン病にかかった人の所在情報がどう伝わり、どのような条件で集団に組み込まれたのかを追った。その結果、所在情報が寄せられる背景には、ハンセン病を忌避し、排除しようとする志向が、組織内の上位権力のみならず、病者が所属する集団や共同体においても共有されていたと指摘している。
中世日本のハンセン病者は、差別されながらも参詣路や交通路など、人々の行き交う開放空間に生きていた。近代以降、国家権力はハンセン病者を強制隔離・療養所収容したが、その「隔離」と比べ、「開放性」があったのだろうか。だがその「開放性」は都市空間における境界性、周縁性を前提としており、施行を受けなければ生きてはいけないという現実があった。また彼らを包摂した非人集団には明確な階層差があり、管理者である長吏には暴力や裁判権をも行使できる権力が備わるとともに、長吏を支配・統制しようとする国家権力の動向も存在した。こうした点から、三枝さんは、中世のハンセン病者もまた「開放性」のもとではなく、中世固有の「隔離と収容」のもとにあった、という。
三枝さんの論文を読んで、私は今に至るまで続くハンセン病に対する差別や偏見が、いかに深くこの社会に根を下ろしていたのかに気づいた。まったく状況が違うとはいえ、同じ感染症であるコロナにどう反応するのかという問題も、過去のハンセン病への対応や、私たちの心性を形作っている長い歴史や文化にまで掘り下げて考えなければいけないのだと感じる。
近世から近代にかけ、国民国家が姿を現すころの欧州について、主に東欧諸国を中心に研究してきた中澤さんは、こう感想を語った。
「これまで近代史研究では、同じ時期の外国を横の空間軸で比較することが多かったが、前近代からの縦の時間軸でどう評価するかという視点が弱かったように思う。三枝さんらの論文を読んで、自分が時間軸から日本という足元を見ていなかったことに気づかされた。ハンセン病を通して、歴史の構造的な問題という重たい課題を突き付けられたような気がします」
「コロナ禍」という言葉の危うさ
一橋大の石居人也さんは「『衛生』と『自治』が交わる場所でー『コロナ禍』なるものの歴史を考える」という論文で、「コロナ禍」という言葉の意味作用について問題を提起した。
石居さんは、「現在を起点に過去を歴史的に問い、歴史を起点に現在をとらえなおす試み」として、近代日本のコレラ対策やハンセン病者の隔離政策をたどりながら、「衛生」という概念がどう日本に定着したのかを振り返る。
近代日本では「感染しない」ことに加え、「感染させない」ことが求められ、やがて「感染させられる」ことへの恐れと一体となって「衛生」が規範として力をもつようになった。この「衛生」には「自治」と「警察」という二項対立の構図があらわれ、あからさまな強権性への忌避が、自発性・能動性の発露へと結びつく回路が開かれた。
そうした考察の上で石居さんは、「コロナ禍」という言葉がもつ意味作用の危うさを指摘する。
「コロナ禍」は、コロナを、あらゆる人の前に立ち現れた一律の危機としてみせる力がある。だがコロナの受け止め方や意味は、人によって状況によって違う。「コロナ」にしても、「ステイ・ホーム」にしても、それぞれ個人にとって意味するものには、途方もない隔たりがある。
だが得体の知れない病を「わたしたち」の「禍」ととらえることは、それに罹患した人や関係者をも、「わたしたち」の範疇から排する心性の喚起につながらないだろうか。
あるいは繰り返し要請された「自粛」は、最終的には個々人の心構えの問題であり、リスク覚悟で別の行動をとる選択肢を排除するものではなかったはずだが、「わたしたち」に「感染させる」リスクを伴う行動をとる人々には、私的制裁が加えられたりもした。「コロナ禍」という言葉は、自己決定を許容しない危機との向き合い方を体現し、それを現実のものにしてはいないだろうか。
石居さんは、そう問題を投げかけ、次のようにいう。
「本来『自治』の範疇にあるはずの『自粛』が、相互監視の対象となり、『警察』の語と結びついた『自粛警察』は、『自治』に内包された陥穽を端的にいいあらわしているように思う」
三枝さんは、この論文について、「私も『コロナ禍』という言葉を安易に使ってしまうが、コロナの『わざわい』が意味するものは人によってまったく違う。『コロナ禍』という言葉を使うことによって、そうした違いを見落とす危うさを教えられた。これを読んでから、『コロナ禍』という言葉を使う時は、括弧でくくるようになりました」という。
私も、この連載などで、安易に「コロナ禍」という言葉を使ってきたが、石居さんの問題提起に目が醒めるような思いがした。言葉には、何事かを指し示す働きがあるかのように見えながら、単純化によって内実の多様性や豊かさを隠し、一定の方向に強く誘導する力がある。それが「クリシェ(決まり文句)」がもつ怖さだろう。
「国民国家」の行方
この論集のもう一つのテーマは「国民国家の行方」だった。一時はグローバル化によって、「国民国家」の役割や機能が低下するという指摘もあったが、すでにコロナ感染がパンデミックになる前から、「アメリカ・ファースト」を掲げる米国のトランプ政権の誕生、英国のEU離脱など、行き過ぎたグローバリズムを修正するかのように、国際協調路線を転換し、「国民国家の復権」を目指す動きが顕在化していた。
国家単位で防疫・公衆衛生を行うパンデミックは、マスク・防護服・ワクチンなど医療資源の国家間争奪が激化したことも相まって、グローバル社会における「国民国家」の在り方を、改めて問いかけることになった。一方ではWHOが主導してワクチンを共同購入し、途上国にも配分するCOVAXなど、国際協調の動きもみられるが、足元では主要国がワクチンを自国最優先で確保し、余剰分を友好国に回して影響力を強める「ワクチン外交」が熾烈化しているのが現実だ。防疫強化や感染拡大防止に名を借りて、ハンガリーやタイ、ミャンマー、中国などが統制を強め、専制化する「COVIDナショナリズム」の高まりを指摘する声もある。
本書の企画を進めていた昨年6月27日、早稲田大学ナショナリズム・エスニシティ研究所(WINE)はオンライン形式でシンポジウムを開いた。テーマは「新型コロナウイルス感染症と国民国家・ナショナリズム」。WINE所長の中澤さんが基調報告をし、すでにご紹介した千葉大の小沢さん、東大の池田さんのほか、本書に論文を寄せた東大の加藤陽子さん、東京都立大の福士由紀さんも討論に参加した。「国民国家」が本書のもう一つのテーマになったのも、同時並行で進むそうした地道な研究の積み重ねの結果だった。
本書に「新型コロナウイルスの副作用―「感染症の人種化(racialization)」を執筆した中澤さんは、緊急事態宣言を次の四つに類型化した。
A 緊急事態宣言を名目に、全権委任を実現し、権威主義的体制を確立したハンガリー・イスラエル型
B 地方自治体の要請はあったが、緊急事態宣言の発出を忌避しつづけた結果、中央政府が政治的に孤立する傾向を持ったブラジル型
C 従来の権威主義的権力機構に依存し、緊急対応条例を発出する中国型
D 個人の自由や自由主義市場経済を重視するも、医療崩壊の危機を前に、緊急事態宣言に踏み切ることになったイタリア・ドイツ・イギリス・アメリカ型
中澤さんによると、欧米ではAとDのいずれかが各国の政治の主流を占めたが、共通の課題として浮上したのが「感染症の人種化」「難民・移民感染者のバイオポリティックス」「国境管理の厳格化・保護主義の活性化」「国民国家の復権」などであった。
中澤さんは主に、首相への無制限の権限移譲をともなう「非常事態法」によって、権威主義体制に移行したハンガリーを例に分析し、パンデミックのような危機的状況下では、民主主義が機能不全を起こし、いとも簡単に移民・難民の排除に結びつきやすいことに警告を発している。この点について、中澤さんは次のように感想を語る。
「パンデミックによって、『国民国家』は強化されていく傾向にあるが、それは19世紀的な国民国家への回帰ではない。さきの軍国主義的な形でもなく、むしろ、国家を使って新自由主義を駆動するような形で補強されていくのではないか。グローバル・ノースの国々は、このパンデミックを通し、多国間協力よりも国民国家の方が、この危機に直結して対処できると考える傾向が強まっているように感じる」
加藤さんは「コロナ禍の世界からみる国家と国民の関係の変容」という論文で、この間、日本ではSNS上でコロナ対応の拙劣さを「インパール作戦」、米国では「団結」の象徴としての「ノルマンディー作戦」など、第2次大戦中の歴史の一コマを例えに持ち出したことに着目した。
今回、こうした大戦の歴史を比喩として持ち出したのは、「コロナ禍を契機に、国家への国民の信頼が揺らぎ、国家と国民の間の信託や『社会契約』というべきものが途切れたとの切実な感覚を、戦後初めてといったスケール感でとらえた人が多かったからではなかったか」という。さらに、コロナ禍を通して米国の「BLM」運動など歴史の見直しが急速に進んだことについても、「国家と国民の関係の揺らぎ」の盾の両面だと指摘する。つまり、表向きの「国民国家復権」の掛け声の裏には、自分たちの生命が国家の無為によって脅かされるような事態に際して、これまで自明とみなしてきた国家と国民の関係が、大きく揺らいだ背景がある、との指摘だろう。歴史の枠組みの変動をとらえる貴重な示唆といえよう。
ネット時代の記録をどう残すのか
この論集では、歴史をめぐる新たな解釈だけでなく、コロナ時代の歴史学の「課題」についても触れられている。
青山学院大の飯島渉さんは「COVID―19と『感染症の歴史学』」の中で、コロナに関するさまざまな記録をどう残していくかが、歴史学が取り組むべき課題の一つだと指摘する。病院や保健所の記録は、個人情報を含むという理由で廃棄されることが多く、感染症への取り組みを検証することが難しい理由でもあった。ネット上の情報も、放っておけば消え去ってしまう。マスクやチラシといったモノも含め、小さな情報や私的な情報を「意図的に記録に残す仕掛け」が必要だろう、と飯島さんは問題提起している。
他方、上智大の北條勝貴さんは、「忘却と変質の相克―COVID―19下の歴史実践の行方」で、「後世の検証のために記録を残そう」という掛け声と共に、コロナ下の暮らしや経験などの記録を残す動きが国内外で始まっていることを具体的に紹介する一方、SNS時代における記録保存の難しさにも警鐘を鳴らす。
情報が氾濫する時代には、情報を削除する「マイナスの操作」ではなく、逆に過剰にすることで社会のリテラシー能力を奪い思考を停止させる「プラスの操作」の方が深刻だという指摘だ。微妙にウソが入り混じる「フェイクニュース」は、新たな情報を加えるというより、作家のジョージ・オーウェルが「1984年」で創出した「ニュースピーク」のような幻惑と混乱をもたらす。
「アーキビストや歴史研究者は、単に情報を収集したり、読解してゆくだけでなく、その生成の方法やプロセスにも介入すべきなのではないか」
北條さんはそういう。これは、マスコミやジャーナリズムにも突きつけられた重い課題だと思う。こうした問題提起について、中澤さんは次のように話した。
「パブリック・ヒストリーをどう実践するかは、現代の新たな課題です。今の時代は文書や映像だけでなく、マンガ、ツイッターなどSNSも含め、ぼう大な発話・発信がなされている。どこかでいったん情報を堰き止めて氾濫を防ぎ、「公衆」と一緒にこれを歴史化する必要があります。史料が限られていたコレラの時代と違って、コロナの時代には、別の情報蓄積の手法が問われている」
この点について、中世を研究する三枝さんはこんな感想を漏らした。
「古代や中世に比べ、近世や近現代史の分野には史料がふんだんにある。史料が限られている古代・中世の分野から見れば、うらやましくもありましたが、無数の情報があったら、それをどう共通の歴史学の俎上に載せていくのかどうか、別の工夫と知恵が必要だと思うようになった。無数の情報の多様性が、権力に都合よく回収される危うさもあります。あふれる情報や資料をどう読み解いていくのか、当事者性を自覚し、批判機能のある歴史学を目指す必要があるのではないでしょうか」
かつて平凡社の「世界百科事典」のプロジェクトを手掛けた編集者に、事典編纂の裏話をうかがったことがあった。平凡社は各分野の若手・中堅の研究者2千~3千人に声をかけ、各項目の執筆を依頼した。小さな項目であっても、事典の執筆にあたっては、ぼう大な労力をかけて資料を集め、過去の研究の成果を調べつくさねばならない。その結果、各分野の執筆者はその後、任された項目を発展させて数多くの論文を書き上げた。「世界百科事典」は結果として、日本の学問水準の底上げの役割を果たせたのではないか、と編集者は述懐した。
今回の歴史学研究会の試みは、小さな最初の一歩かもしれない。締め切りまでの時間も限られ、各論文の分量も多くはない。それでも、この小さな若木には、将来の歴史学に豊かな繁りをもたらすに違いない数多い枝が芽吹いていると思った。
ジャーナリスト 外岡秀俊
●外岡秀俊プロフィール
そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員
1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。