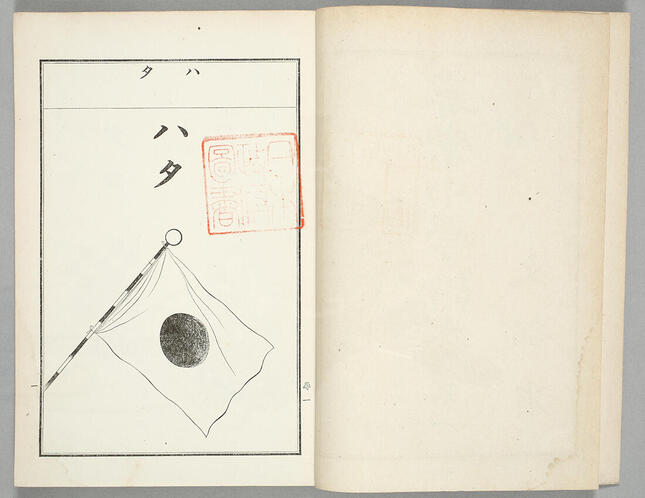国定教科書が初めて使われたのは、1904(明治37)年であった。日露戦争が始まった年である。それまで比較的自由に編集されていた教科書も、国の意志のもとに統一されることになった。しかしこの第1期では児童生徒に特に強い国家への帰依を盛り込んでいたわけではない。
ところがその6年後の1910(明治43)年の第2期国定教科書は、第1期と大幅に変わってしまう。なぜだろうとの思いがするが、理由はすぐにいくつか挙げられる。重要な理由として二点を挙げておこう。その第一は、1905(明治38)年に終わった日露戦争後の社会不安である。日露戦争は国力を賭けた戦いであったが、その戦いの後の国民の不安が反政府の方向に向かった。増税への不満、戦争批判などの世論が広まった。1908(明治41)年に「戊辰詔書」が出され、国民へは天皇への忠義が強く求められることになったのは、そういう社会不安を鎮静化させようとの政府の思惑であった。
「不遜思想」抑えようとした政治指導者
第二は 反政府運動が思想化していき、社会主義、アナキズムなど政府側から見たら、「不逞思想」が影響力を持ち始めたのである。
無政府主義者と言われる幸徳秋水を首謀者に仕立て上げた大逆事件(1910=明治43年)などは、政治指導者の不安を示している。こういった不逞思想を排斥しなければとの焦りも生まれた。
政治、軍事指導者は、このような風潮をなんとか抑えようと考えたのであろう。治安立法での弾圧とともに時代を担う世代への思想教育を徹底しなければと考えた節もある。それが教科書国定化の強い意志と見ることができる。あえて付け加えておくが、教科書は子供が学ぶに過ぎず、それほどの影響はないではないかとの論もある。しかしこれは基本的な誤りを犯している。それを説明しておかなければならない。
現代のように「表現の自由」が保証されている時代なら、あらゆる情報メディアから多くの知識、情報を得ることができる。しかしこの頃は、教科書は知識の源泉の最大にして、最高の媒介物であった。子供が教科書で学ぶことは、その父母たちへのメッセージでもあった。最もわかりやすい例として、昭和の国定教科書では天皇は神と教えたが、子供が家に帰ってそういうと、大正時代に教育を受けた父母の世代は、「そんなことはない」と反論する。しかし、子供との間のコミュニケーションを通じて時代の枠組みを父母に理解させるのである。
さらに教師達は、生徒に家庭内のことや父母との会話を作文という名目で書かせることにより、天皇神権説を否定する父母を浮かび上がらせて、危険思想の持ち主として治安当局に伝えるようなことも密かに行われていた。教科書の存在を決して軽視できないのである。明治43年の国定教科書の改定は、そういう時代への第一歩だったのである。