現状
世界第2位の自動車大国

池袋にあるトヨタ自動車の常設展示場 「アムラックス東京」
日本は世界で2番目の自動車大国で、自動車業界は日本のリーディング産業である。2輪車を合わせた2002年の製品出荷額は43兆1630億円と、全製造業の出荷額に占める割合は16%、機械工業全体では35%と、日本経済を支える重要な基幹産業の1つとなっている。世界的に見ても2003年の国内生産は1029万台で世界総生産6065万台の17%、1993年まで続けた世界トップの座は明け渡したものの、米国の1207万台に次いで2位をキープしている。
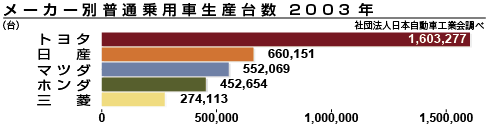
中でも目覚ましいのは日本メーカーの国際的な展開だ。トヨタ自動車と、子会社の日野自動車、ダイハツ工業を合わせたグループの2003年の生産台数は682万台にも達し、米フォードを初めて抜いて米GMの824万台に次ぐ世界第2位。ホンダも米国などでのRV(ルクリエーショナル・ビークル=レジャー向けの多目的自動車)のヒットで296万台とフォード、フォルクスワーゲン(VW)、ダイムラー・クライスラー、仏プジョー・シトロエンに次ぐ世界7位に躍進した。一時、経営危機に陥った日産自動車も仏ルノー出身のゴーン社長主導によるリストラに成功、297万台と世界8位にまで復活している。ソニー、松下電器産業、日立製作所などかつて世界をリードしたエレクトロニクス業界が米インテルや韓国サムスンの後塵を拝してしまった今、自動車は日本では数少ない国際的なリーディング産業の1つとなっている。
国際化とリストラで復活を遂げる
米国のビッグ3の追い上げや1995年の1ドル80円を上回る超円高、1990年代の金融システム不安のなか、1990年代に日本の自動車業界は苦境に陥った。米国での販売不振によって大幅な赤字に転落、金融システム不安も手伝って資金調達に苦しんだ日産自動車は、ダイムラー・ベンツや仏ルノーとの資本提携を模索した結果、1999年にルノーと資本参加を含むグローバルな提携契約に調印し、ルノーの傘下入りを選択した。

東京銀座の日産本社
一時、米クライスラーから独立した三菱自動車もリコール問題や米国販売の苦戦で経営不振が表面化、2000年にはダイムラー・クライスラーとの資本提携に踏み切っている。さらにスズキ、富士重工業がGMとの資本提携に進んだ結果、従来の11社体制は崩壊、日本の自動車業界は、トヨタ自動車グループ(トヨタ・日野自動車・ダイハツ工業)、ホンダの民族系2社と外資系(日産自動車=ルノー、マツダ=米フォード、三菱自動車=ダイムラー・クライスラー、いすゞ自動車、スズキ、富士重工業=GM)の2グループに色分けされることになった。
こうしたなか、劣勢だった日本メーカーが巻き返すことができたのは、国際化とリストラが進んだせいだ。

日産自動車のカルロス・ゴーン代表取締役社長兼CEO
トヨタ自動車は、米国での現地生産の一段の強化や仏やアジアでの現地生産に着手するとともに、米国市場でそれまで手薄だったRVを積極的に投入、ホンダも北米での現地生産を強化するとともにオデッセイなどRVの品揃えの強化を進めている。一方、ルノー傘下入りした日産自動車は、村山工場の閉鎖など国内生産体制の再編、人員の大幅削減、部品メーカーの系列の見直しなどリストラを進めるとともに、米国新工場の建設、ピックアップトラックの投入を積極化。トヨタ自動車が2003年度連結純利益で1兆円を上回る利益を上げるなど、リコール問題が発覚し不振が続く三菱自動車を除いて業績は上向き、日本メーカーは復活を遂げている。
歴史
マイカーブーム、11年で10倍以上の高成長

トヨタ自動車創業者の豊田喜一郎(右)と、その父で自動織機の発明者である豊田佐吉(左)
日本の自動車業界は第2次世界大戦後、わずか30年の間に奇跡的とも言える高成長を達成、1983年には米国を抜いて世界最大の自動車大国となった。成長の原動力となったのは、モータリーゼーションの開花と輸出の成長だ。戦後間もなくは、トラックを中心とした小規模生産にとどまっていたが、1955年の国民車育成要綱、1961年の割賦販売法の制定を経て、1960年代の高度成長時代にモータリーゼーションが開花した。1960年にわずか40万台だった国内販売は、1963年に100万台を達成し、1966年には200万台にまで拡大した。
モータリーゼーションが始まったころは、トラックなど法人需要が中心で、乗用車もハイヤー、タクシーなどに利用されることが多かったが、日産自動車のサニー、トヨタ自動車のカローラが登場した1960年代後半からは本格的なマイカーブームが到来した。国内販売は乗用車、商用車合わせて68年には400万台を突破、1969年には初めて乗用車の販売台数が商用車を上回った。1960年にわずか48万台だった国内生産台数も、国内需要の拡大で1970年には500万台の大台を突破、わずか11年で10倍以上の高成長を遂げている。
輸出が伸びて、国内生産1000万台乗せ
1960年代後半から70年代になると、輸出が急速に成長、国内生産拡大の牽引役となった。なかでも大きいのが、カローラ、サニーなど乗用車の拡大だ。1965年当時、輸出は19万台にとどまっていたが、乗用車が輸出の中核となると、輸出は急速に拡大し、1970年には100万台、1973年には200万台に突破した。その後も輸出増の勢いは衰えず、1976年には371万台、1980年には600万台に迫った。国内生産もこうした輸出の拡大を背景として1970年の528万台から1980年には1104万台にまで拡大、米国に次ぐ自動車生産国となった。国内生産の拡大とともに日本製自動車の地位も向上している。

トヨタ自動車が1955年1月に発表した初の大量生産乗用車、トヨペットクラウンRS
当初、輸出は米国車に比べて低価格であることを武器として米国市場でシェアを獲得していった。ところが、1971年のニクソン声明をきっかけとした変動相場制への以降によって円高が進展、また1973年には第1次オイルショックが発生し、原材料輸入国である日本にとってコストが上昇した。
こうしたなか、日本の自動車業界では、NC(数値制御)工作機械、ロボットの導入などによる多品種少量生産への対応、社内提案制度による原価低減や品質の改善、エンジンと燃費改善、ボディの合理的設計など省エネへの対応、排ガス規制への対応などを積極的に行った結果、日本車の国際的な競争力は大きく向上した。
貿易摩擦が激化、現地生産の時代に
1980年代は日本車の世界市場でのシェアが拡大、「トヨタ生産方式」に代表される日本型の生産システムが欧米で注目されるなど、日本自動車業界の黄金時代となった。

多く歴史的な車やレーシングカーを展示している日産自動車座間記念車庫
米国市場でシェアを大幅に拡大した1970年代後半から米国との間で貿易摩擦問題が表面化。1980年、GM、フォード、クライスラーのビッグ3が巨額の赤字を計上すると、貿易摩擦はさらに激化、1981年5月には対米乗用車輸出の自主規制策が打ち出された。
自主規制によって輸出に枠がはめられるなか、日本メーカーは輸出車種を大衆車から中高級車に切り替えて採算を維持する一方、1982年にホンダがオハイオ州でアコードの生産を開始したのをはじめとして次々に米国での現地生産に乗り出した。ホンダに続いて1983年には日産自動車がテネシー州シマーナ、1984年にはトヨタ自動車がカリフォルニア州でGMと合弁の現地生産を開始した。1980年代後半になると、マツダがミシガン州、三菱自動車もクライスラーと組んでイリノイ州に進出したほか、富士重工業といすゞ自動車が合弁でインディアナ州で現地生産を開始している。
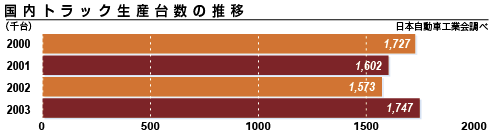
一方、成熟化が懸念されていた国内市場も、乗用車の複数保有の広がりによって安定した伸びを示した。1980年代後半になると、バブル景気のなか、1988年1月に日産自動車が発売したシーマが高級車としては記録的な売り上げを記録するなど、より高級な「3ナンバー車」(普通車)の売り上げが急速に拡大した。輸出はプラザ合意に端を発した円高の進展で1985年の763万台をピークとして大きく減少したが、国内販売は1980年の502万台から1990年には778万台にまで拡大、国内生産も1990年、1349万台と過去最高を更新している。
バブル崩壊後、供給過剰になる
バブル崩壊後の10年は、「ジャパン・アズ・No.1」の象徴ともなった自動車業界にとって試練とともに、次の21世紀に向けた雌伏の時代となった。1990年に778万台に達した国内販売は、バブルの崩壊とともに減少に転じ1993年には647万台にまで減少した。一方、米国メーカーは1980年代の後半からリストラを徹底するとともに開発段階から日本のシステムを採用して開発期間を短縮化、デザインの活性化も図って、GMのサターン、フォードのトーラスなど品質を重視した車が市場に投入された。1993年には日本車を上回る低価格を実現したネオンをクライスラーが発売、米国市場で巻き返しに転じ、日本車の輸出は1994年には500万台の大台を下回ることになった。国内生産は国内、輸出の不振で大きく落ち込み、1990年の1349万台から1994年には1055万台と300万台近くも減少した。バブル期に計画したマツダの防府工場の増設、日産自動車の九州新工場、トヨタ自動車の九州新工場が稼働していたこともあって、供給過剰が表面化、1995年には日産自動車が座間工場の閉鎖に追い込まれている。
国際的再編が進行、11社体制が崩壊
日産の業績はその後、一時、持ち直したが、1990年代後半、米国販売の不振が表面化した。そして、1997年の金融システム不安、さらに1998年の独ダイムラー・ベンツと米クライスラーの合併という内外での激震が走ったなか、1999年、仏ルノーとの資本提携を発表する。

中古自動車販売店
RVのヒットで一時、日産自動車を追い上げた三菱自動車も米国での販売不振、リコール問題で国内販売が低迷に転じた結果、業績が急速に悪化、2000年にダイムラー・クライスラーの傘下入りを決断した。さらにGMのいすゞ自動車、スズキに対する出資比率の引き上げ、GMと富士重工業との資本提携と再編が相次いだ結果、これまでの業界地図は一変した。
日本の自動車業界では、1966年に日産自動車がプリンス自動車を合併して以来、トヨタ自動車と日産自動車の2強体制が確立。以来続いてきたトヨタグループ(トヨタ自動車・日野自動車工業・ダイハツ工業)、日産グループ(日産自動車・日産ディーゼル工業・富士重工業)、独立系(ホンダ、三菱自動車、スズキ)、外資系(マツダ=フォード、いすゞ自動車=GM)の11社体制(マツダは1979年、フォードの傘下に、三菱自動車は1993年、クライスラーから独立)は崩壊した。
現地生産の拡大、強化で国際企業へ脱皮
一時、1ドル90円を切る水準まで円高が進むなか、1995年には日米自動車交渉が決裂し、日本の自動車メーカーは対日制裁リスト(日本からの高級車13車種に対する100%関税の賦課)の発表という緊急事態にまで追い込まれた。対日制裁はトヨタ自動車をはじめ日産自動車、ホンダ、マツダ、三菱自動車が策定した自主経営計画「グローバルプラン」によって回避することができた。
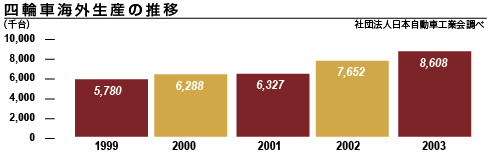
当初、北米での生産能力の増強、外国製部品の調達拡大など自主計画は日本メーカーへの大きな負担となると見られていたが、実際には日本の自動車メーカーが真の国際企業に脱皮する好機となった。トヨタ自動車をはじめとして日本メーカーは既存の工場の生産能力を引き上げたことに加えて、トヨタ自動車がインディアナ州、ホンダがアラバマ州への進出を決定するなど現地生産の強化に乗り出すとともに、エンジンなど重要部品の現地生産も強化している。ここで注目されるのは、日本メーカーが新たな工場や増設ラインで生産することに決めた車種は、ビッグ3の得意分野とされた高級車やピックアップトラックなどRVであることだ。これでRVが主流をしめている米国メーカー追撃の態勢を整えることができたうえ、重要部品の現地生産を開始することで経営基盤を強化することも実現している。
将来を展望するための3つのポイント
ポイント1
売れる車を作り続けることができるか
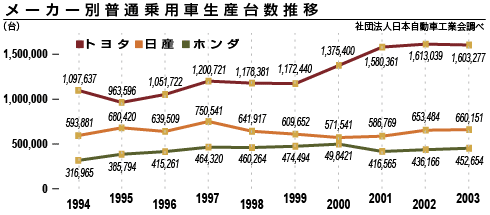
1990年代後半まで日本車を急速に追い上げた米国メーカーが再び劣勢に陥った最大の要因は、売れる車づくりを怠ったことにある。米国では1990年代、従来の乗用車に替わって、ピックアップトラックをはじめとするRVが売れ筋の車種となった。
こうしたなか、トヨタ自動車は、GM、フォードなどビッグ3の対抗車種となる大型のRVを相次いで投入、これまで日本車が手薄だったRVでのラインナップを充実させ、米国市場でのシェアアップを図っている。これに対してビッグ3は既存RVに安住し、新型RVの開発を怠った面は否めない。

フランスのバランシエンヌにあるトヨタ自動車の工場
また、RVが主流になったとはいえ、セダンも依然として大きな市場を形成しているが、ビッグ3はここでも新型車の開発を進めることができなかった。なかでも1990年代半ば、トヨタ自動車のカムリ、ホンダのアコードを抜いて米国でベストセラーカーとなったフォードのトーラスの場合、レンタカー市場にも拡販した結果、中古車価格の低下を招いた。新型車の開発を怠ったことと相まって、2000年代に入ると販売が急減、フォードのシェア低下の要因の1つとなっている。これに対して、トヨタ自動車、ホンダはカムリ、アコードのフルモデルチェンジを逐次実施、販売台数を維持した。このため、RVのヒットがシェア増に結びついた。
劣勢に追いやられたGM、フォードなども巻き返し策に出てくることは確実なだけに、日本メーカーがヒットに奢らず新型車の開発を続けていくことが、今後も好業績を続けるかどうかの大きなポイントになる。
ポイント2
次世代エンジンの開発競争

2004年のF1グランプリ
自動車のエンジンは、これまでガソリンが主流だった。ところが、排気ガス対策など環境規制の強化や地球温暖化問題で省エネルギー車が求められ、1997年、トヨタ自動車がハイブリッドカー・プリウスの販売を開始したことで、自動車エンジンのパラダイム転換が起こった。プリウスはガソリンエンジンと電気で回るモーターの動力を交互に利用して走る車だが、環境に優しいことが受けて発売直後からヒット、2003年までに16万台が生産されている。トヨタ自動車では、エスティマ、クラウンなどにも一部のモデルについて、ハイブリッドエンジン車を導入するとともに、2003年秋にはプリウスのフルモデルチェンジを実施、ハイブリッドカーの強化を進めている。さらにホンダもハイブリッドカーのインサイトをすでに発売、主力車種の1つであるシビックにもハイブリッドエンジン車を導入している。
ここで難しいのは、どのエンジンがガソリンエンジンに代わる主役となるか分からないことだ。燃料電池車が水素を燃料とするため、CO2の排出量が少ない、熱効率が高い、騒音・振動が少ないという点でもっとも注目されている。だが、実用化まではまだ時間がかかるうえ、普及には水素ステーションの設置などインフラの整備が必要になる。また、燃料電池車が先進国で普及したとしても、中国やインドなど新興諸国で売れるようになるまでは、この地域の所得レベルが先進国並みに向上することが前提条件だ。現在、ハイブリッドカーではトヨタ自動車をはじめとする日本メーカーが先行しているが、燃料電池車など他の次世代エンジンでも優位性を保つことができるのかどうか。今後の注目点の1つだろう。
ポイント3
中国など新興市場を開拓できるか
米国や欧州、日本など先進国マーケットが成熟段階に入った今、世界の自動車メーカーにとって新たな主戦場となるのが、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)や東欧などいわゆる新興市場だ。なかでも各国のメーカーにとってもっとも重要な市場となるのが、中国だ。中国の自動車生産は2003年に450万台とフランスを抜いて米国、日本、ドイツに次ぐ世界第4位となったが、年々高成長を続けて2010年には現在の日本並みの1000万台にまで達すると見られている。

銀座4丁目にある日産自動車のショールーム
現在、中国での現地生産は日本メーカーがこれまで米国、欧州など主要輸出マーケットでの現地生産を優先せざるをえなかったこともあって、欧米メーカーがリードしている。なかでも独VWは上海汽車工業、第一汽車との合弁でパサート、ジェッタなどを生産、中国市場で高いシェアを占めている。
一方、出遅れた日本メーカーも、1990年代後半から中国戦略に着手した。広州汽車との合弁でホンダがアコード、オデッセイを生産しているほか、日産自動車も東風汽車と広州市や四川省でサニーの現地生産を行っている。第一汽車傘下の天津汽車とヴィオスの合弁生産を始めたトヨタ自動車は、広州汽車とも合弁を設立、カムリの現地生産を行う準備を進めている。21世紀の最大市場となる可能性をもつ中国戦略の正否が今後の世界の自動車業界地図を大きく左右するカギとなるだろう。






