歴史
1985年まで国家独占
日本の通信産業は明治政府の近代国家建設とほぼ並行して発展してきた。
経営形態は、欧州各国と同様、国家の独占事業であり、1985年まで国家独占が
続いた。

歴代の家庭用電話機

歴代の公衆電話
第2次世界大戦で日本の通信網は壊滅的打撃を受けたが、1953年から国内通 信は日本電電公社、国際通信は株式会社でありながら政府の管轄下にあったK DDが、それぞれの分野を独占、民間企業の自由な参入は許されなかった。
国家独占ながら戦後の通信網復旧は急速に進み、1979年にはダイヤルを使っ て全国にかけることができるようになり、通信網の整備は着実に進んだ。しか し、独占事業の非効率、無駄遣いなどが次第に表面化し、1980年代の行政改革 の中で、政府は英国のBT民営化にならい、電電公社の民営化を進めた。通信 事業への競争政策も導入された。1985年の民営化後、長距離分野で国鉄系の日 本テレコム、民間から第二電電(DDI)、道路公団系の日本高速通信などが 参入した。国際通信には二社が参入した。その結果、長距離、国際電話の通話 料は次第に低下、競争の成果が現れた。それまで電電ファミリーと呼ばれた少 数の企業群によって独占されていた通信機器の市場開放も進み、端末の自由な 販売で、電話機の価格も低下した。
NTTが分離、分割される
長距離分野の競争は進んだものの、市内通信分野は民営化されたNTTの独 占が続き、NTTの分離、分割を求める声が競争事業者、通信政策当局からあ がった。 この論争は民営化後10年以上続き、1999年、NTTは持ち株会社 のもと、長距離、国際通信のNTTコミュニケーションズ、地域通信を受け持 つNTT東日本、西日本の3社に分離、分割された。携帯電話会社のNTTド コモは1992年に一足早くNTTから分離された。 通信市場は外資にも開放 され、BT、AT&T、ケーブルアンドワイヤレスなどが資本参加などの形で 参入したが、激しい市場競争に敗れ、外資は相次いで撤退した。
iモードが爆発的に普及
日本の携帯電話普及台数は2004年に8000万台を超え、携帯電話サービスは 1979年から自動車電話サービスとしてスタートしていたが、市場が爆発したの は1994年、デジタル携帯に周波数が割り当てられ、新たな競争が始まってから だ。 市場爆発のもうひとつの要因は、1999年に導入されたiモードと呼ばれ る携帯電話からのインターネットアクセスサービス。着信音に好きなメロディ ーを選べる着メロサービス、ゲーム配信、時刻表配信サービスなど携帯電話に よるインターネットアクセスは日本で独特の発展を見せた。携帯のテンキーだ けによるメール文字入力は若者の得意技となった。カメラつき携帯も若者の支 持を獲得、インターネットと携帯の融合が急速に進んでいる。
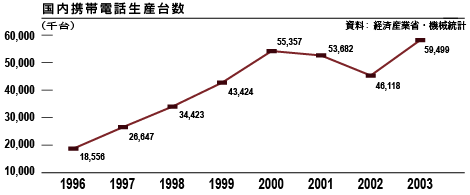
携帯向けサービスではさまざまなコンテンツプロバイダーが出現した。携帯 電話会社や他の決済サービスを利用して、1カ月数百円以下という手ごろな価格 設定が成功の要因となった。事業規模を拡大した企業は海外進出を始めた。